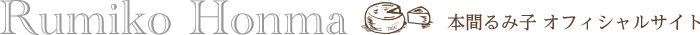4年ぶりのフランス農業祭
2024年09月27日投稿
フランスではプロフェッショナルのためのチーズサロンが隔年で開催されます。これに合わせて、シャンパーニュとブリ周辺を巡る旅を開催したのが4年前、2020年2月でした。
2020年3月以降はコロナ禍となり、イベントはすべてが中止や延期となってしまいました。
したがって今冬の2024年2月は、4年ぶりのフランス訪問となりました。
■国際農業見本市(農業祭) Salon International de l’Agriculture
毎年2月末から3月初旬にかけて行われる農業見本市。この巨大なイベントがパリで行われているというのは、日本の感覚ではすぐに理解できないかもしれません。メトロ12号線。ポルト・ド・ヴェルサイユ駅近くに建設される会場は東京ドーム10個分!
フランス各地から集められた牛、羊、山羊、豚、ウサギ、鶏、馬、ロバなどたくさんの家畜が一堂に会し、コンクールも開催されます。
さすがに農業大国フランスの奥深さが感じられる国内でも最も人気の高いイベントで、会期中の入場者は数万人を記録し、海外からの来場者も年々増えています。
会場に入ると、日本では見たことがないようないろいろな種類の牛がゾーンごとにいたり、搾りたての乳を使ってシャレ(山小屋)風につくられたブースでチーズ製造の実演があったり、牛好きにはたまりません。
毎年、その年のシンボルとして選ばれたスター牛がいるのも面白い仕掛け。バスやメトロのポスター、入場券、ガイドブックやエコバックにまでその顔が登場するのですから会場ではまるでアイドル扱いです。
今年のスター牛はノルマンディ牛のOREIETTEちゃん5歳!
でも、仲間たちから隔離されてちょっと寂しそうでした。
会場では、プロの料理人のデモンストレーションがあり、フランス各地のブースでは買い物も試食もできて、大人も子供も楽しそう。
コンクールは家畜、チーズやワイン、農作物など約20のカテゴリーで行われます。
私は1997年から毎年ここでチーズコンクールの審査員を務めていますが、いつも勉強させていただいています。
①2024年のスターはノルマンディ牛のOREIETTE 5歳。入場券のモデルにも


②ノルマンディ牛は頭とお腹は白く、目の周りがパンダのように黒か茶色。疲れてぐったり!


③ホルスタイン牛のコンクール

④ぺライユ・ド・カバスを販売するロジーヌ・ドンブルさんと息子。
ドンブルさんと会ったのは1996年のサロン・ド・フロマージュ。
翌年に訪ねたことを思い出します。


⑤山のチーズ製造のデモンストレーションが行われていました

■サロン・デュ・フロマージュ Salon du Fromage
農業祭の一画で隔年開催されているチーズサロンは招待状がないと入れないプロフェッショナル限定の商談エリアです。


このサロンに通うようになったのは、1991年~1995年まで一緒に仕事をしていた湯川廉子さんのおかげ。フェルミエを創業した頃は私も渡仏は1年に1回がやっとでした。
そんな私に「もっと積極的に行動しなさい!」とお尻を叩いてくれたのが彼女だったのです。
今ではチーズ商も生産者もEU各国からやってくるようになりましたが、私が参加し始めた90年代まではフランスの生産者だけで規模は小さく、日本人といえば私たちだけでした。
アットホームな会場には「作り手の見えるチーズ」があり、ここで出会ったチーズを輸入して日本のチーズファンに紹介することにワクワクしました。
この時は4年ぶりに再会したことに杯をあげて、またの再訪を約束!
1995年に始めた生産者を巡る旅は、このサロンでの出会いがあればこそ実現したものです。
●スペインからマンチェゴ・アルテサーノの「フィンカ・ラ・プルデンシアーナに会えました。アルバレス氏から息子にバトンタッチ。

●2019年、第4回モンディアル・デュ・フロマージュで優勝したオランダ代表のEvert SCHONHAGE。2018年2月に案内してもらった農家製ゴーダは忘れられない思い出です。

●2023年9月のブラ祭りで訪ねたジョリートさんに再会!
フロマージュ・ド・ミテスの金剛丸由美さんがご一緒でした。

●マヌエル・マイアさんは1999年、FOODEXにオリーヴオイルとマルメロ(メンブリージョ)で出展。マルメロを輸入販売したことが縁で、2000年にポルトガルのチーズ産地を案内していただきました。
ポルトガルチーズといえばマイアさん。チーズビジネスをすることになったのは私のおかげだと感謝されています!


ポルトガルを代表する羊乳の
ケイジョ・セーラ・ダ・エストレーラ

かりんのペースト「マルメロ」は
チーズとよく合います。
●まるでミュージシャン!
MOFのXavier はいつも陽気で楽しい!

●カゼアリア
シチリアで開催された「チーズアート」で酔っ払いチーズ「ウブリアーコ」に出会い、カゼアリア社を訪問。家族一丸となり創業者の類のないチーズを開発しています。
いつ訪ねても、心づくしの対応に、いつも心地よく酔っぱらってしまいます。
創業者のアントニオは亡くなられてしまいましたが、二代目のアレッサンドロが頑張っています。

アレッサンドロのオリジナル、ブルージンズ、おいしくいただきました。


酔っ払いチーズ カゼアリア
●パカール
パカールのルブロッションに出会ったのはサロンでした。
ジャンフランソワの息子に幻の美しいカビがはいったブルー・テルミニヨンをカットしていただきました。

ジュニパーで香りづけたトム、酔っ払いのトムもおいしくいただきました

●ブラ祭りでもあった、カールハインツ・ベルトルド(左)とロッソ社のエンリコ。
エンリコはアルピニストで山のチーズのプロです。

●クリスチャンの友人、ジョン・カール。
彼は頭の回転が抜群でユーモアもあって頼れる人です。
1990年初頭に立ちあげたチーズ専門季刊誌「アリスティーアス」の英国編(1993年)は彼のアレンジで生産者を訪ねました。

●「CHEESE CHEESE CHEESE」の制作者。
ウィル・スタッドは好奇心旺盛で何事もポジティブ。
メルボルンでチーズショップ「カレンダー」を経営していた頃、オーストラリアでは長期熟成以外の無殺菌乳のチーズの輸入が禁じられており、フランスからのロックフォールが差し止めになって廃棄処分になったことがありました。処分を巡って世界中のチーズ仲間に署名運動をして政府に訴えたのです。もちろん私も日本の署名運動で応援しました!
日本のロケは岡山の吉田牧場、長野の清水牧場、北海道の共働学舎を紹介。一緒に旅をしたことは懐かしい思い出です。

●私のビジネスパートナー、クリスチャン(中央)。 引退しても、みんなから声をかけられて忙しい!

●ピエルッチに出会ったのは1996年のサロン・デュ・フロマージュ。
2002年にコルスを訪ねるツアーを開催。家族みんなで出迎えてくれたことも懐かしい思い出です。

 コルシカチーズ
コルシカチーズ
●アラン&ソフィー・ジョソーム
シェーヴルのコンクール「フロマゴラ」が開催されていた頃に出会ったアラン。
1993年はニーム、94年はサント・モール・ド・トゥーレーヌ、95年はカオールで開催。
2005年に彼はオリジナルチーズ、ドーム型の「トピニエール」を開発して大ヒット。2012年にはひとまわり小さい「トピネット」をリリース。
山羊を大事に育てている農場をもう一度訪ねたい。

●ピック
ユニークなシェーヴルが魅力的なピックに出会ったのもサロンでした。
いま、日本には輸入されていませんが、ピック社の取り組みに感動して訪ねたことを思い出します。



●レティヴァのベルナール・ゴダール
2001年にAOCを取得したレティヴァを訪ねたのが7月。9月に牛が下山する「デザルパージュ」のお祭りがあると知り、9月にツアーを企画して訪ねました。
3度目の訪問は2014年。共同の熟成カーヴを建設したベルナール・ゴダールの努力あってこそ、いまも70軒の生産者がいるそうです。

●INAOの会長を務めていたアンドレ・ヴァラディエさんの功績が大きいライオル。
1950年代の終わりころ、年間生産量が25トンにまで落ち込む危機に直面し、1960年に「山の青年協同組合」を設立。郷土料理「アリゴ」をレンジでつくる商品を開発。
今回のサロンははいってすぐのところにあり、熟成別のライオル、簡単にできる料理デモンストレーションもありました。ピエルリッチさんの料理センスのおかげでライオルに魅了された人が多いと思います。
いま、日本人の川本美季さんが働いています。


●シャウルスのトップランナー、ランセ社
フレッシュのブリヤ・サヴァランとデリス・パパイヤが人気。
いつも穏やかなディディエとジュリエットです。

●スヤン
カルフォルニアのアンダンテファームのスヤン・スキャラン。
韓国に生まれ、結婚してカリフォルニアのソノマに住み、シェーヴルを製造。
もともと音楽の素養があり、チーズの名前はフィガロやアンダンテなど、彼女ららしい名前をつけています。ピアノを弾き、料理をつくり、人生を謳歌。
パリ滞在中はアパルトマンを借りて友人を招いて食卓を囲む。クリスチャン、LAQUEUILLEのオリヴィエ、FINE CHEESEのジョン。2人のジャーナリストはベルリンのウルスラと、イタリアとアメリカを行き来するクリスティーナ。この日はウルスラが持ってきてくれたドイツのチーズを楽しみました。ドイツも新しいチーズが増えていることを実感。



スヤンの食卓
●ワインの名城地マコンから北に5km
山羊2000頭を飼うシュヴネ家。二歳にして山羊がペットだったというティエリー。
シャロレは彼の自慢のシェーヴルです。

●ロドルフ・ル・ムニエ
2005年、シラ国際見本市のプラトーコンクールで見事優勝を勝ち取ったロドルフ・ル・ムニエ。その時のテーマが「ショパンとマチス」。
幼い時からチーズの手伝いのかたわらで親しんできたピアノ、絵画、彫刻、文学などそのすべてがチーズを魅力的に表現するための要素だったと言います。
あれから20年近く。彼の活躍は目が離せません。